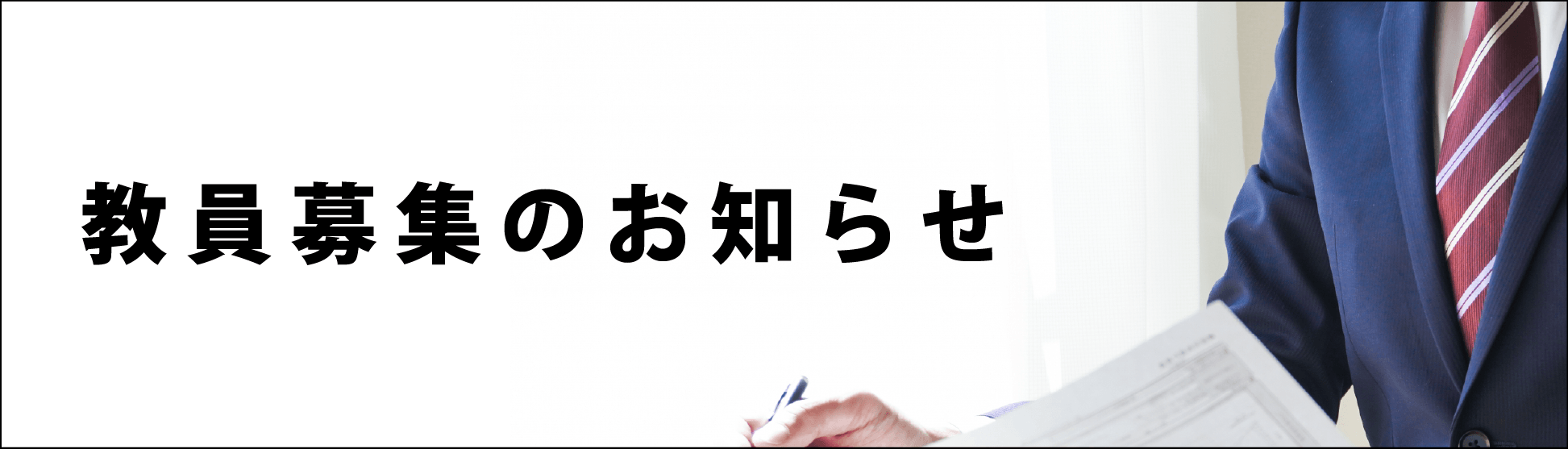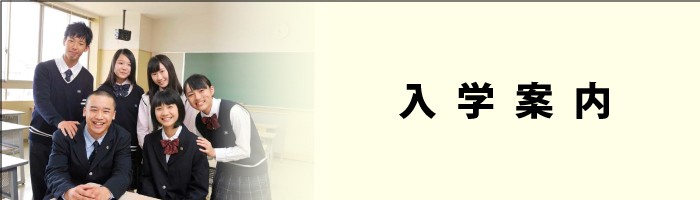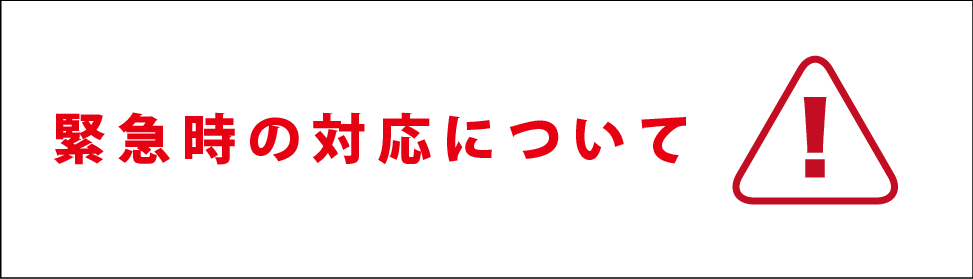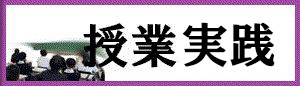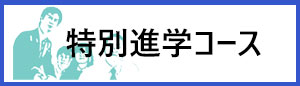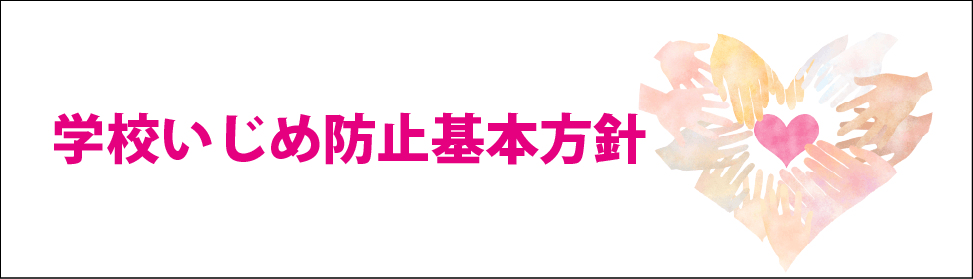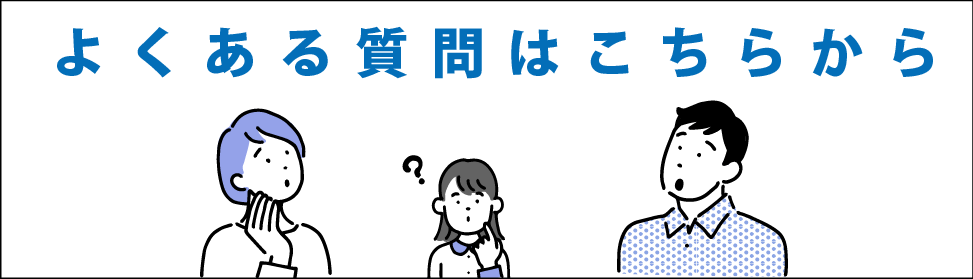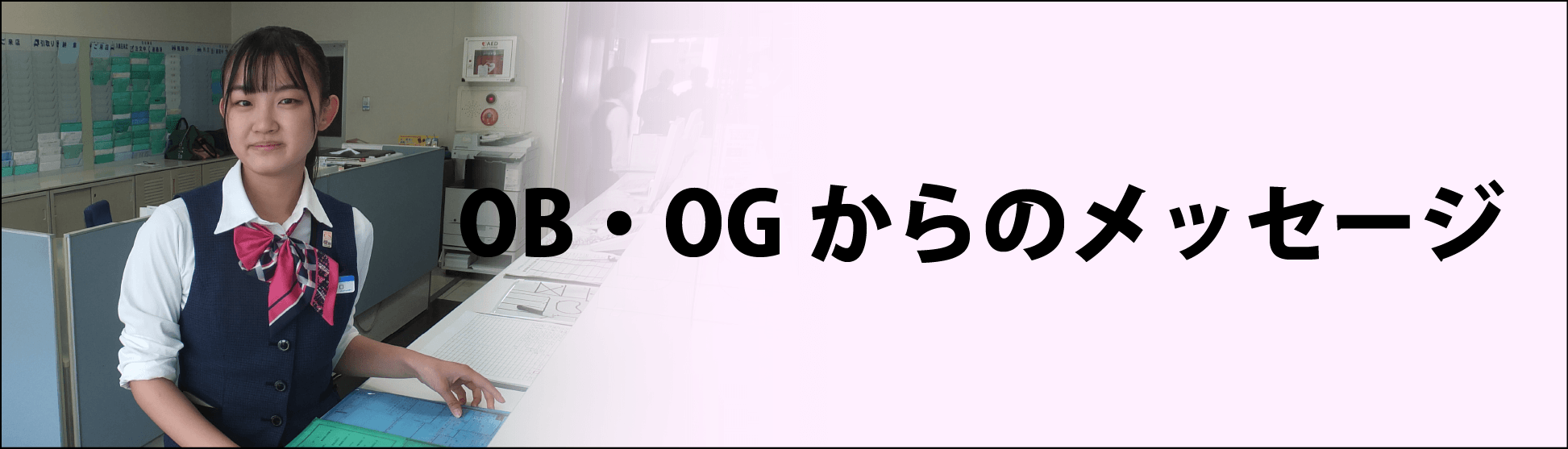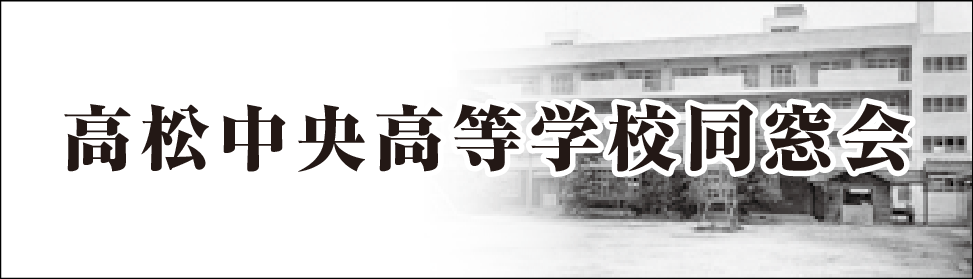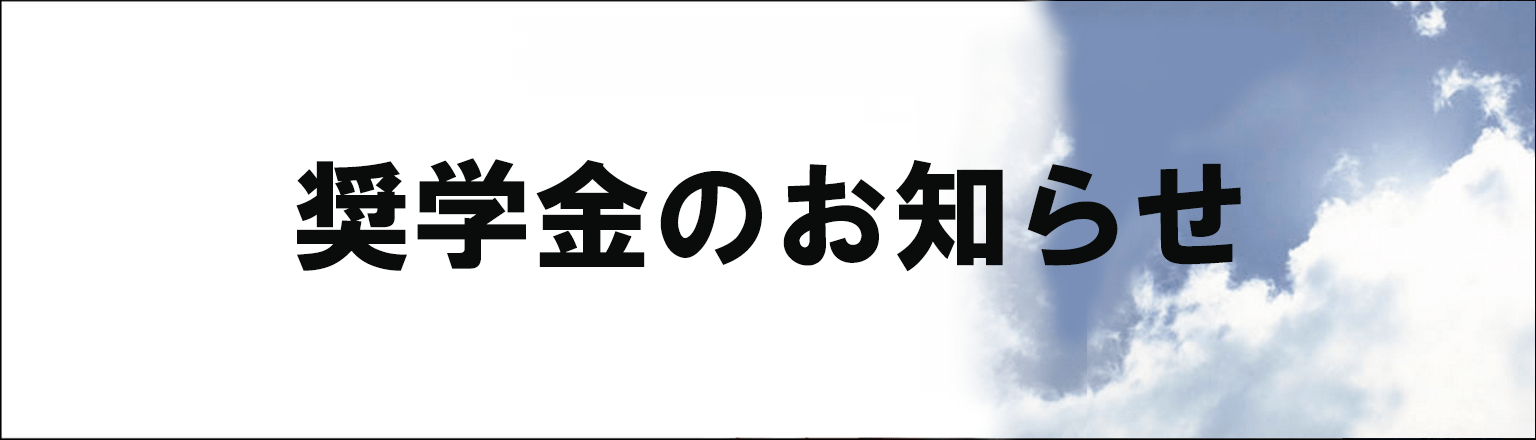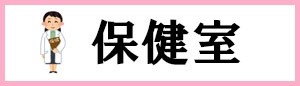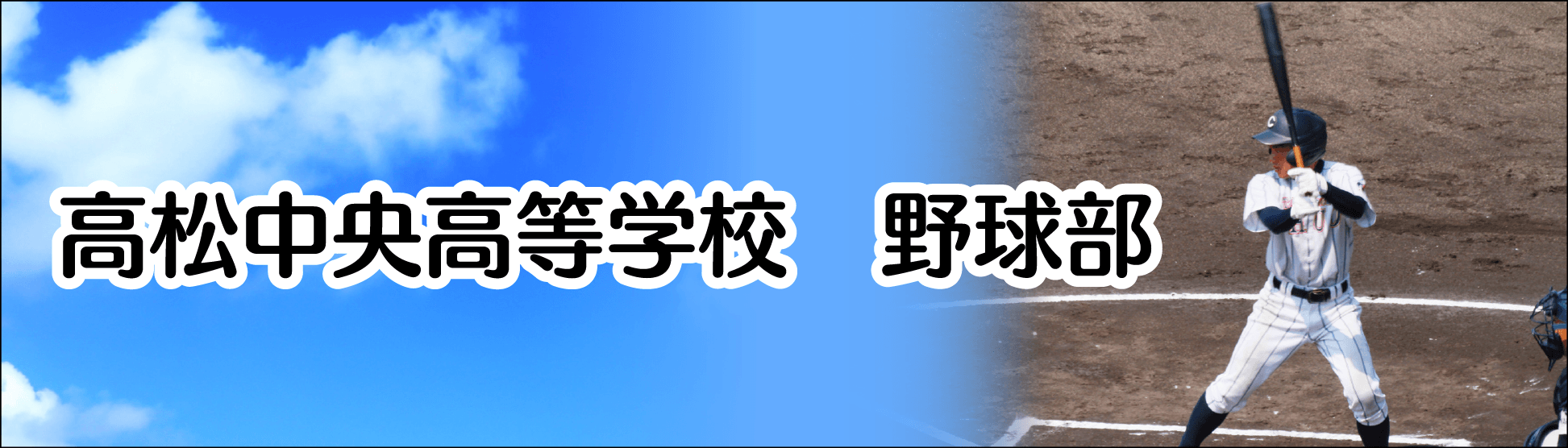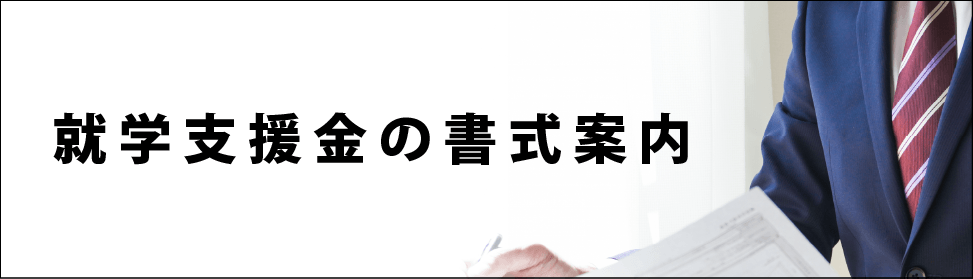合田龍司さん(24)日鋼サッシュ製作所 本社営業部設計課(平成29年度普通科特別進学コース卒業)

●数学だけが得意でした
中学時代から数学が得意というか、数学だけが得意でした。高校でも数学以外は調子がいい時で平均点。国公立大学は国語・英語・数学・社会・理科の5教科すべてが受験科目。私立大学の3教科であれば得意な数学で他の2科目の差を埋めたらいいものの、国公立大学は他の4科目の差も縮める必要があり、半ばあきらめていました。本格的に進路を考え始めた2年生の時、自分のためにあるような試験方式の国公立大学を母親から聞きました。その試験方式はセンター試験の数学の配点比率が高く、二次試験は数学のみという、高知工科大学経済・マネジメント群のC方式。無事合格できました。
大学入学時は、特進コースで大変お世話になった担任の田所先生のような数学教師を目指そうと決めていました。でも、自分の得意とする応用問題を解くことより証明の暗記が増え、自分には合っていないなと1年目に方針転換。数学を生かせる職業として建築業界に興味を持ちました。建築の世界の中でも「広い分野で仕事をするより、専門的な仕事が自分には向いている」と思い、建具の設計に携われる現在の会社に就職しました。
●建具設計にやりがいを感じています
建物の設計図を基に、CADで建具の図面を描く仕事をしていますが、数学を解くための思考回路や空間認識能力が役立っています。空間認識でいえば、二次元、三次元を同時にイメージできる人、例を挙げるとサイコロの展開図を即座にイメージできる人は設計の仕事が向いていると思います。
近年の建具には、建物の構造や仕様によって耐風圧性や水密性、気密性、耐熱性、遮音性などさまざまな性能が求められており、設計の段階でそれらの性能をすべて決めなければなりません。弊社の建具はオーダーメイドなので、同じ図面を描くことがなく、毎回が初挑戦。大変ですが、やりがいがあります。設計から製作、施工まで一貫して請け負っているので、自分が設計した建具の出来上がりを直接見ることができるのも、やりがいにつながっています。
入社3年目ですが、新人の指導にも当たっていて、中堅として頑張らないといけない立場です。グレードの高い建具の作図や新しい商品の開発に携わることを目標に頑張っています。
●90分の課外授業と学食
高校時代の思い出ですか? ひたすら勉強した記憶しかないのですが、その中でも90分の課外授業と学食は今でも覚えています。
90分の課外授業のおかげで国公立大学に合格することができ、大学進学後も1コマ90分の講義にすぐ慣れました。慣れずに寝ている学生も居ましたが(笑)。課外授業といえば、担任の田所先生。とにかく熱があって、面倒見のいい先生でした。数学が得意な生徒にはそのレベルに合わせた教え方をしてくれるのですが、数学が苦手な生徒にもとことん付き合ってくれる、数学が苦手な文系の生徒でも数学の成績がぐんぐん伸び、同期の男子は9人全員が国公立大学に進学しました。ここまで尽くしてくれる先生がいるのかと、影響を受けました。僕の場合は、課外授業のおかげで学習塾に通う必要もなく、学校内で勉強が完結。ありがたかったです。
勉強漬けの学校内で、息抜きできるのが学食の時間。他愛もないことをしゃべりながらクラスメートとテーブルを囲んだり、休憩時間に軽食を買ったり。楽しい思い出です。


●おいしいものは本場に限る
趣味は、本場でおいしいものを食べ歩くこと。大学生の時に、高知でカツオのたたきを食べて、驚き、感動したのがきっかけで、旅行先の名物を意識して食べるようになりました。「今まで食べてきたカツオのたたきは、別の食べ物。うまいものは本場に限る」と。
最近は仕事が忙しくて泊まりがけの食べ歩きからはちょっと足が遠のいていますが、以前は金曜の夜から2泊3日で県外に出て、名店やら隠れスポットをはしごしていました。麺類が好きで、お気に入りの広島にはしょっちゅう出かけています。
●「あきらめないこと」「周囲に感謝」
後輩に伝えたいのは、「あきらめないこと」と「周りの環境に感謝すること」。
僕の場合は、センター試験の結果が思わしくなかったため、二次試験の数学でほぼ満点を取る必要があったのですが、10年分以上の過去問を解き、難関大学を目指す同期と同レベルの問題を一緒に解いていたので合格することができました。
得意科目を最大限に伸ばしてくれた先生、先生と一緒に大学選びを助けてくれた両親、数学だけは負けたくないという気持ちにさせてくれたハイレベルな同期には今も感謝しています。
仮に共通テストで失敗しても二次試験に向けてあきらめずに最後まで頑張り、サポートしてくれる周りの方たちに感謝して高校生活を頑張ってほしいと思います。
(令和6年12月取材)